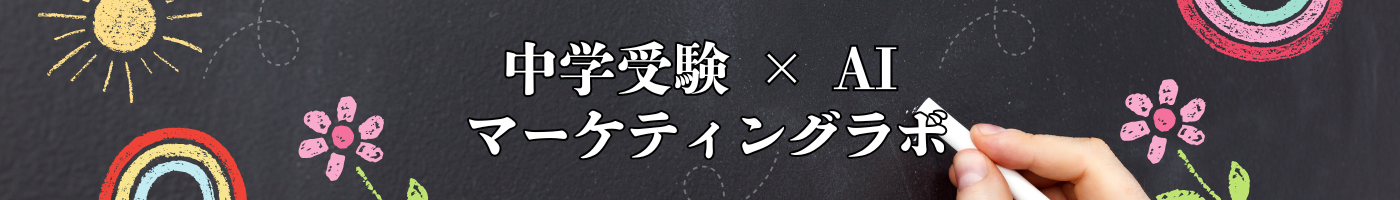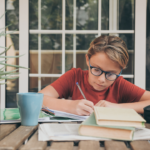小学生の中学受験とピアノの習い事を両立するのは、多くのご家庭にとって大きな挑戦です。 首都圏ではSAPIX(サピックス)や日能研などの大手進学塾に通いながら、幼い頃から続けてきたピアノをどうするか悩む親御さんも少なくありません。「勉強に集中させるためにピアノを辞めるべきか?」「続けさせたいけれど時間的に厳しいのでは?」といった葛藤は、決して他人事ではないでしょう。この記事では、小4から小6にかけて変化する受験勉強のスケジュール感や、ピアノを続けることのメリット、両立が難しくなる時期と乗り越え方、さらにピアノを辞めるか迷ったときのアドバイスについて、保護者の目線に寄り添って詳しく解説します。
小4から小6:塾のスケジュールはこう変わる

中学受験の準備は年々本格化し、塾の通う頻度も学年によって増えていきます。小4の段階では、首都圏の大手塾(SAPIX、日能研、四谷大塚、早稲田アカデミーなど)の多くが週2日の通塾ペースです ( 週に何回通うことになる?4大受験塾の時間割とかかるお金を徹底比較 )。授業時間は夕方5時頃から夜8時前後までとされ、週末は隔週でテストがある程度で、比較的ゆとりがあり他の習い事と両立しやすい時期です (中学受験 4年生から「日能研」に通わせると、どんな毎日になる? – 中学受験情報局『かしこい塾の使い方』)。
しかし小5になると状況が変わります。授業日は週3日に増える塾がほとんどで ( 週に何回通うことになる?4大受験塾の時間割とかかるお金を徹底比較 )、学習内容も一気に高度化します。多くの塾では小5の1年間で受験に必要な全範囲の学習を終えるカリキュラムとなっており、その分宿題やテストも増え、学習量は小4時の約1.5倍にもなります ( 週に何回通うことになる?4大受験塾の時間割とかかるお金を徹底比較 )。実際、「5年生は勉強量が格段に増えてかなりハード」という声もあり (中学受験で習い事はいつまで続けるべき?両立は可能? | ダイヤモンド教育ラボ)、この頃から家庭学習との両立に苦労し始める子が増えてきます。
小6になるとさらに忙しさが増すのが一般的です。塾の授業日は週4日以上となることも珍しくなく、土日も模試や志望校別特訓などでほぼ埋まります ( 週に何回通うことになる?4大受験塾の時間割とかかるお金を徹底比較 ) (中学受験で習い事はいつまで続けるべき?両立は可能? | ダイヤモンド教育ラボ)。例えば日能研では6年生で週4回程度の授業+毎週のテストがあり、四谷大塚では学校別対策コースを含め週5日通塾するケースもあります (中学受験で習い事はいつまで続けるべき?両立は可能? | ダイヤモンド教育ラボ)。SAPIXでも6年生は平日の授業に加え、土曜日に75分×4コマの志望校特訓が組まれており (中学受験で習い事はいつまで続けるべき?両立は可能? | ダイヤモンド教育ラボ)、事実上**「毎日が受験勉強」**という生活になります ( 週に何回通うことになる?4大受験塾の時間割とかかるお金を徹底比較 )。塾が休みの日も山のような宿題や過去問演習があるため、小6は勉強にフルコミットせざるを得ない時期と言えるでしょう。
こうしたスケジュールの変化を見据え、多くのご家庭では小4から小5にかけて徐々に習い事を整理し始めます ( 週に何回通うことになる?4大受験塾の時間割とかかるお金を徹底比較 )。特に土日に拘束時間の長いサッカーや野球などは、試合と塾特訓が両立しにくく断念する例も少なくありません ( 週に何回通うことになる?4大受験塾の時間割とかかるお金を徹底比較 )。ピアノの場合も、小5~小6に向けて「いつまで続けるか」を考える時期が必ず訪れます。では、ピアノを続けることで得られるものは何でしょうか?次の章で見ていきましょう。
ピアノを続けるメリット:集中力アップと情緒の安定
忙しい受験勉強の合間にピアノを続けることには、単に「音楽の才能を伸ばす」以上のメリットがあります。ひとつ目は、集中力や忍耐力の向上です。ピアノを習う子どもには集中力が高く粘り強い傾向があるとされ (〖ピアノが上手い子は学力もピカイチ?〗音楽で育てる賢さのヒミツとは? | piano-gift)、実際にピアノ演奏には譜読み・指の動き・リズムなど複数の要素に同時に注意を払う必要があるため、自然と高い集中力が養われます (〖ピアノが上手い子は学力もピカイチ?〗音楽で育てる賢さのヒミツとは? | piano-gift)。長期間コツコツと練習を積み重ねる経験は忍耐力も鍛え、受験勉強にも通じる力となるでしょう。また、「ピアノ経験者には勉強ができる子が多い?」という興味深いデータもあります。例えば東京大学生の約半数が幼少期にピアノを習っていたという調査があり (〖ピアノが上手い子は学力もピカイチ?〗音楽で育てる賢さのヒミツとは? | piano-gift)、音楽経験が学力向上に寄与する可能性を示唆しています(もちろん相関関係であり因果関係ではないものの、励みになるエピソードですね)。
二つ目のメリットは、情緒面への良い影響です。受験期は子どもにとって精神的にプレッシャーやストレスがかかる時期ですが、音楽はそのストレスを和らげ心を安定させる効果があります (幼児期は「脳の土台づくり」に最適。音楽が「考える力 … – FQ Kids)。脳科学者の茂木健一郎氏も「楽器演奏者はほぼ100%、情緒的に安定して穏やかだ」と述べており、それだけ音楽は脳(前頭葉)への栄養になるということです (幼児期は「脳の土台づくり」に最適。音楽が「考える力 … – FQ Kids)。ピアノを弾く時間は、子どもにとって**受験勉強から一時解放される“心のオアシス”**になり得ます。慣れ親しんだ曲を弾いたり好きな音色に触れたりすることで気分転換でき、「勉強だけ」の生活による精神的な張り詰めを緩和してくれるでしょう。
さらに、ピアノには身体的な面での効果もあります。意外かもしれませんが、ピアノで鍛えた指先の力は鉛筆の筆圧にも好影響を与えます。近年は子どもの指の力が弱く字も薄くなりがちと言われますが、重いピアノの鍵盤をしっかり押さえる練習によって指の筋力がつくと、長時間書いても疲れにくく集中力も高まるそうです (習い事と中学受験は両立可能か?親子二人三脚で受験を乗り越える道とは | 東大家庭教師友の会) (習い事と中学受験は両立可能か?親子二人三脚で受験を乗り越える道とは | 東大家庭教師友の会)。受験では記述答案を何時間も書き続ける体力・集中力が問われるため、ピアノで培った「書く体力」は思わぬ強みになるかもしれません。
このように、ピアノを続けることは勉強面・精神面の双方でプラス効果をもたらします。音楽でリフレッシュできる子は勉強への切り替えもうまく、時間管理能力も養われるという指摘もあります (習い事と中学受験は両立可能か?親子二人三脚で受験を乗り越える道とは | 東大家庭教師友の会)。実際、受験期に適度な息抜きを持つことは10~12歳の子どもにはとても大切であり (習い事と中学受験は両立可能か?親子二人三脚で受験を乗り越える道とは | 東大家庭教師友の会)、ピアノはその健全な息抜きの役割を果たせると言えるでしょう。
両立が難しくなるのはいつ?小5後半~小6が正念場

メリットが多いピアノとはいえ、塾の勉強との両立が特に難しくなるタイミングがあります。多くの家庭で山場となるのが、小5の後半から小6にかけてです。小5の夏以降は塾のカリキュラムが本格化し、夏期講習や模試も増えて一気に忙しくなります。「小5の後半から成績が急降下してしまった」という声もあるほどで (SAPIXに通う小学6年生の母ですが、正直な話、八方塞です …)、勉強量の増加についていけず余裕を失う子も出てきます。特に小5の秋から冬にかけては、学校行事(運動会や学芸会など)と塾の両立で疲労がたまりやすく、ピアノの練習時間を確保するのが難しく感じられる時期でしょう。
小6に進級するタイミングで、ピアノを続けるか一旦休止するかの決断を迫られるケースも多いようです。「小6からは勉強一本に絞ろう」とピアノをやめる子、「受験が終わったら再開しよう」とこの一年間だけお休みする子など、対応は様々です。塾側も「6年生では勉強のみに集中する環境づくりが大切」と助言することがあり (中学受験で習い事はいつまで続けるべき?両立は可能? | ダイヤモンド教育ラボ) (中学受験で習い事はいつまで続けるべき?両立は可能? | ダイヤモンド教育ラボ)、親としても習い事を絞らざるを得ないと感じるかもしれません。
実際、小6になると平日の塾日以外も家庭学習や過去問演習でギュウギュウ詰めになり、「毎日ピアノを練習する余裕はとてもない」というのが実情でしょう (ピアノと中学受験~両立は大変?ピアノ教室ができること<高知市・西久万ピアノ教室> – 高知市の西久万ピアノ教室)。あるご家庭では、小5の終わり頃に「塾の時間が増えてピアノを弾く時間が取れなくなってきた。でもこれまで続けてきたピアノを辞めてしまうのはもったいないし、本人も続けたいと言っている。どうすればいいだろう?」と悩まれたそうです (ピアノと中学受験~両立は大変?ピアノ教室ができること<高知市・西久万ピアノ教室> – 高知市の西久万ピアノ教室)。まさに**「受験勉強に専念させるため習い事を全部やめるべきか、それとも続けさせるべきか」**という岐路に立つのが、小5後半から小6にかけてなのです。
このような時期には、親も子もストレスを感じやすくなります。ピアノの上達も停滞しがちで、「あまり練習できず上手くならないのにレッスン料を払い続ける意味があるのか…」とジレンマに陥る保護者も少なくありません (ピアノと中学受験~両立は大変?ピアノ教室ができること<高知市・西久万ピアノ教室> – 高知市の西久万ピアノ教室)。一方で、子どもにとってピアノ教室は小さい頃から通い慣れた心の拠り所でもあります。新しい塾の先生やクラスメイトとの緊張感に晒される中、ピアノの先生との信頼関係やこれまで積み重ねた成功体験が得られる場所は心を安定させる効果があります (ピアノと中学受験~両立は大変?ピアノ教室ができること<高知市・西久万ピアノ教室> – 高知市の西久万ピアノ教室) (ピアノと中学受験~両立は大変?ピアノ教室ができること<高知市・西久万ピアノ教室> – 高知市の西久万ピアノ教室)。この安心感は受験直前のメンタルケアとしても貴重です。
要するに、小6前後が両立の一つの転機になりますが、その乗り越え方次第でピアノの継続がプラスにもマイナスにも働き得るのです。次の章では、実際にピアノと受験勉強を両立させているご家庭の工夫例を見てみましょう。
塾とピアノを両立する工夫:先輩家庭はここを工夫した
両立が難しいとはいえ、工夫次第で「ピアノも勉強も」充実させているご家庭もあります。先輩たちは一体どんな工夫をしているのでしょうか?いくつか具体例をご紹介します。
- 練習時間の見直し(短時間集中型に): 「毎日1時間練習」は受験期には非現実的。そこで練習量は思い切って減らし、その代わり質を重視します。例えば平日は塾の宿題前の15分だけ指慣らし程度に弾き、週末に30分まとめて練習するといった具合に、短時間でも細く長く続けるパターンです。「細々とでも自分で時間のやりくりをしながら、一つのことを続ける経験ができた」という声もあり (中学受験とピアノの両立、どう乗り越えた? – いずみ中央音楽教室)、限られた時間で効率よく練習することで逆に集中力が上がることもあります。
- レッスン曜日・頻度の調整: 塾のない日や負担の少ない時間帯にレッスンを入れる工夫も効果的です。塾通いが本格化する小5以降、ピアノレッスンを隔週に減らしたり、日曜の午前中(模試がない日)に振り替えるなどスケジュールを柔軟に調整する家庭もあります。また、レッスン時間もコンパクトに30分だけにしたり、発表会やコンクールへの参加は受験が終わるまで見送ることで、「細く長く続ける」体制に切り替えます。あるピアノ講師の方も「週1回1時間のレッスンで勉強時間が多少減ったとして、それで志望校に落ちることはないのでは」と述べています (いつまでピアノ続ける?問題 中学受験を見据えて | 木村ピアノ教室 Diary)。無理のない頻度に抑えれば、ピアノが過度な負担にはならないでしょう。
- ピアノの位置づけを変更(癒やし・リフレッシュ重視に): 受験期のピアノは「上達のため」というより**「気分転換と維持」のためと割り切るのもポイントです。実際に、男子御三家など難関校に合格したある生徒さんは小6の10月末までピアノレッスンを続け**、11月~1月の入試直前3ヶ月だけ休んだそうです (いつまでピアノ続ける?問題 中学受験を見据えて | 木村ピアノ教室 Diary)。この生徒さんは6年生の間、新たな難曲には挑戦せず「以前弾いた曲やポップスなど、気分良く弾ける曲」を先生と選び (いつまでピアノ続ける?問題 中学受験を見据えて | 木村ピアノ教室 Diary)、練習もほとんどゼロでOKというスタイルに切り替えました (いつまでピアノ続ける?問題 中学受験を見据えて | 木村ピアノ教室 Diary)。それでもレッスンでピアノに触れる時間は「頭がスッキリして良い気分転換になった」そうで (いつまでピアノ続ける?問題 中学受験を見据えて | 木村ピアノ教室 Diary)、勉強漬けの日々の中で週一回ほっと笑顔になれる時間になっていたとのことです。まさにピアノをストレス発散の場にする工夫ですね。
- 先生や周囲の協力を仰ぐ: 両立には家族や先生方のサポートも欠かせません。ピアノの先生に事情を話してレッスン内容を柔軟に変えてもらう(受験期はゆったりペースでOKにしてもらう等)、また自宅での練習を親御さんが見守りつつ短時間で切り上げる工夫をするなど、周囲と連携して子どもを支えることが大切です。最近はオンラインレッスンを取り入れる教室も増えていますので、移動時間を節約して自宅でレッスンを受けるのも一案でしょう (いつまでピアノ続ける?問題 中学受験を見据えて | 木村ピアノ教室 Diary) (いつまでピアノ続ける?問題 中学受験を見据えて | 木村ピアノ教室 Diary)。実際、レッスン会場までの往復に1時間以上かかるようであればその時間も惜しいですから、できる範囲で環境を整えてあげると負担がぐっと減ります。
これらの工夫によって、「ピアノと受験勉強の両立なんて無理だと思っていたけど、意外とうまく回っている」というケースもあります。特に子ども自身がピアノを好きで続けたい気持ちがある場合、上手に力を抜きつつ継続することで勉強の合間の癒やしとなり、結果的に勉強の効率も上がることが期待できます。もちろん、お子さんの性格や体力にもよりますので、無理をしすぎない範囲で取り入れてみてください。
ピアノを辞める?続ける?迷ったときのアドバイス
**「このままピアノを続けて本当に大丈夫だろうか?」**と悩んでいる方へ、最後にいくつかアドバイスをお送りします。
- お子さんの気持ちを最優先に: まず大切なのは、お子さん本人がどう感じているかです。ピアノが好きで「できれば辞めたくない」と思っているのか、それとも「勉強が忙しいなら仕方ないかな」と割り切っているのか。あるQ&Aサイトでも「お子様の意思を尊重してあげてください。本人が満足しているなら十分です」という経験者の声が寄せられていました (中学受験とピアノの両立についてご意見お願いします。小4の子供がいますが、年長か… – Yahoo!知恵袋)。無理に続けさせても本人がストレスを感じては逆効果ですし、逆に本人が本当は続けたいのに親の判断で辞めさせてしまうと後々後悔が残るかもしれません。まずはお子さんと本音で話し合い、「どうしたいか」を聞いてみることをお勧めします。
- “一時休止”という選択肢: 辞めるか続けるかの二者択一だけでなく、「受験が終わるまで一旦お休みする」という柔軟な選択肢も考えてみましょう。小学校卒業までにピアノを完全にやめてしまうと、新しい中学校生活で再開のきっかけを掴みにくくなる場合もあります。 (習い事と中学受験は両立可能か?親子二人三脚で受験を乗り越える …)ピアノ教室の先生によれば、一度離れてしまうとなかなか戻らないケースも多いそうです(環境が変わり別の部活や趣味に夢中になるなど)。ですから、受験直前の半年~1年だけ休講扱いにしてもらい、合格後に復帰するという方法は、「やめっぱなし」にならないための工夫です。ただしこの場合も、お子さんに「受験が終わったらまたピアノやりたい?」と確認して、意欲が残っているか見極めましょう。合格のご褒美として憧れの曲にチャレンジさせてあげる計画を立てるのも良いモチベーションになります。
- これまでの積み重ねは無駄にならない: 「せっかく何年も続けてきたのに、ここで辞めたらもったいない」という思いは多くの親御さんが抱くものです。実際、年中・年長から習い始めて小4・小5で辞めてしまうと、譜読みや指の動きなどせっかく身につけた技術を手放すことになり残念…と感じる先生もいます (いつまでピアノ続ける?問題 中学受験を見据えて | 木村ピアノ教室 Diary)。しかしご安心ください。たとえ一旦区切りをつけることになっても、ピアノで培った力は決して消えません。 音楽的な基礎力や感性、集中力や忍耐力といった非認知能力は、お子さんの中に蓄えられていますし、何より「ここまでやり遂げた」という自信は大きな財産です。それに、音楽の素養がある子は将来また機会があれば必ず戻ってこれます。中学・高校で部活の合唱伴奏者に抜擢されたり、大学で軽音楽を始めたり、大人になって趣味で再開する方も大勢います。ですから、「辞める=全てが無駄になる」と悲観しすぎず、今後の人生のどこかで役に立つ経験になったと前向きに捉えてください。
- メリハリをつけて最後まで走り抜く: もし「やはり受験が終わるまでは続けたい」という結論になった場合は、メリハリをつけて両立生活を走り抜く覚悟を決めましょう。 小6の夏以降は特にしんどいですが、「あと○ヶ月で一旦ピアノはお休みだからそれまでは頑張ろうね」と声をかけたり、塾の無い日に5分でも鍵盤に触れたら思い切り褒めてあげたりして、モチベーションを維持してください。先述のピアノ講師の例では、小6の夏までは続けるのも一つの目安と言われています (いつまでピアノ続ける?問題 中学受験を見据えて | 木村ピアノ教室 Diary)。一般的には小5の終わり頃に区切りをつける子が多い中、ピアノが大好きなお子さんなら夏までも十分両立可能でしょう。夏期講習が始まる前に最後の発表会に出たり、好きな曲を先生と仕上げたりと、悔いのない区切りをつけられるとベストですね。「ここまでよく続けてきた」という達成感は、受験勉強へのエネルギーにもきっと転換できるはずです。
保護者の皆さんへ: 中学受験とピアノの両立は、簡単ではないぶん悩みも尽きないことと思います。ですが、お子さんにとって何が一番良いのかを模索し、時には立ち止まりながらも決断していく過程そのものが、親子の成長に繋がるはずです。ピアノも勉強もどちらも頑張った経験、あるいは涙をのんでピアノを一時中断した経験――どんな選択であっても、お子さんの未来にとって貴重な学びとなります。 大切なのは家庭ごとのベストなバランスを見つけること。周囲の体験談や情報も参考にしつつ、ぜひ親子で納得のいく答えを見つけてください。頑張るお子さんと支えるご家族にとって、ピアノが少しでも心の支えやプラスになりますように応援しています!
参考資料・出典: 中学受験情報局(かしこい塾の使い方) (中学受験 4年生から「日能研」に通わせると、どんな毎日になる? – 中学受験情報局『かしこい塾の使い方』)、名門指導会コラム ( 週に何回通うことになる?4大受験塾の時間割とかかるお金を徹底比較 ) ( 週に何回通うことになる?4大受験塾の時間割とかかるお金を徹底比較 )、ダイヤモンドオンライン (中学受験で習い事はいつまで続けるべき?両立は可能? | ダイヤモンド教育ラボ) (中学受験で習い事はいつまで続けるべき?両立は可能? | ダイヤモンド教育ラボ)、東大家庭教師友の会 (習い事と中学受験は両立可能か?親子二人三脚で受験を乗り越える道とは | 東大家庭教師友の会) (習い事と中学受験は両立可能か?親子二人三脚で受験を乗り越える道とは | 東大家庭教師友の会)、ピアノ講師のブログ (いつまでピアノ続ける?問題 中学受験を見据えて | 木村ピアノ教室 Diary) (いつまでピアノ続ける?問題 中学受験を見据えて | 木村ピアノ教室 Diary) (いつまでピアノ続ける?問題 中学受験を見据えて | 木村ピアノ教室 Diary)他。