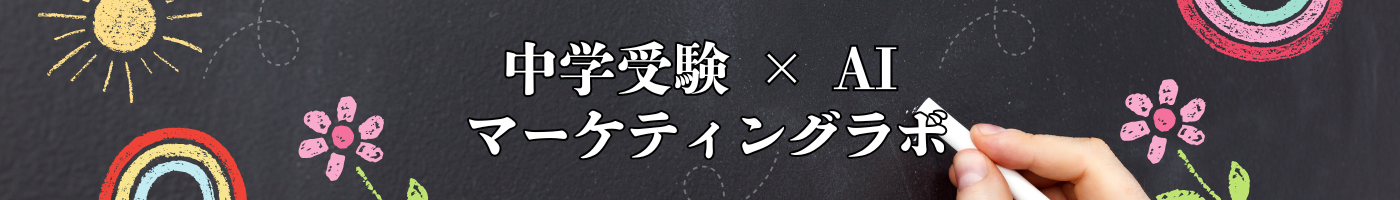(1)はこちらから↓
四谷大塚模試で見る「偏差値と志望校合格」の真の関係性とは?(1)
親が知っておくべき模試結果の正しい見方

模試の成績表が返ってきたとき、数字や判定に目が行くのは当然ですが、保護者の方にはぜひ**結果の「中身」**をじっくり見る習慣を持っていただきたいです。正しい模試結果の見方として、以下のポイントを押さえておきましょう。
1. 合格判定の意味を正しく理解する:まず判定記号(A~Eなど)が示す確率の意味を把握しておきます。多くの模試では、A判定=80%以上の合格可能性、B判定=60%程度、C判定=50%程度、D判定=30%程度、E判定=20%以下といった基準になっていますysmedia.jp。これは「その偏差値帯の子の〇%が合格した」という統計上の意味であり、あなたのお子さんが〇%の確率で受かるという予言ではない点に注意してください。判定50%(C)だからといって「2回受ければ1回受かる」という個人の成功確率ではなく、「同じ成績の子100人中50人が合格する水準」という集団統計なのですysmedia.jpysmedia.jp。合格判定は未来を決めるものではなく、現在地を示すものにすぎません。この前提を親御さんが正しく理解していれば、模試結果に過度に振り回されず冷静なサポートができるでしょう。
2. 偏差値を見るときは母集団と誤差も考慮:四谷大塚模試の場合、母集団は首都圏の受験生を中心に大きく安定していますが、それでも偏差値には誤差の幅がありますameblo.jp。偏差値が数ポイント上下するのは誤差の範囲とも言われameblo.jp、判定のボーダーライン上ならたまたま今回B判定でも次回はA判定…といったことも起こり得ます。したがって、偏差値○○と出たからといって1~2ポイント差で一喜一憂しないことも大切です。特に受験直前期は全受験生の成績が収れんしてくるため、偏差値の微差よりも科目別の得点率や弱点克服の度合いに目を向けるほうが有意義です。
3. 科目別・設問別に分析する:模試成績表には科目ごとの偏差値や得点、設問ごとの正答率など詳細なデータが載っています。これらを活用し、お子さんの強み弱みを具体的に把握しましょう。例えば、「算数は偏差値60と健闘しているが、理科が偏差値45と足を引っ張っている」「社会のある分野の正答率が低い」といった具合です。偏差値の高低は科目配点の影響もあるため、得点率や正答率も合わせて見ると実態がつかみやすくなります。「他の受験生の正答率が80%以上なのに自分は間違えた問題」がどれかなどもチェックしましょうysmedia.jp。それは周りの多くができているのに自分だけ落としている問題であり、早急に補強すべき単元を示していますysmedia.jp。
4. 成績の推移を見る:単発の結果だけで判断せず、できれば直近数回の模試の推移を追います。成績表にも前回までの偏差値推移が載っていることがありますが、上がり下がりの傾向を読むことが大切です。「夏以降右肩上がりできているか?それとも頭打ちか?」といった点を見れば、志望校合格への手応えや課題が見えてきますjisyusidou.com。例えば偏差値が徐々に伸びているなら勉強方法がうまくハマっている証拠ですし、判定がCからBに上がってきたなら第一志望合格も現実味を帯びてきたと言えますjisyusidou.com。逆に伸び悩んでいるなら勉強のやり方を見直す必要があるでしょう。模試は合否の予言ではなく成長の記録と捉え、過去から現在への成長曲線を見る視点を持つことが「正しい見方」ですjisyusidou.com。
5. 結果に対する親のリアクションを一定に:見方とはやや異なりますが、保護者の方自身が模試結果とどう向き合うかも重要です。良いときも悪いときも、感情の振れ幅を抑え安定した態度で接することを心がけましょう。お子さんはテストの出来が悪いとき自覚して落ち込んでいるものです。そのときに親まで酷く落胆したり叱責したりすると、お子さんはさらに自信を無くしてしまいますlettuceclub.net。逆に良かったときに舞い上がりすぎるのも、次回以降プレッシャーになることがあります。模試の度に大喜びしたりガッカリしたりせず、常に**「温かく見守る」スタンスでlettuceclub.net、「今回は弱点が分かって良かったね」「前回より良くなったね」と前向きな声掛け**をするようにしましょう。親御さんの安定したサポートがあれば、お子さんも模試結果を冷静に受け止め次の行動に移しやすくなります。
模試の結果で目標設定を効果的に行う方法

模試結果を受け取ったら、それを今後の学習計画・目標設定に活かしましょう。判定や偏差値に振り回されないためにも、結果を建設的に使っていくことが肝心です。以下に、模試結果を活用した目標設定のステップを紹介します。
ステップ1:課題を洗い出す – 成績表をじっくり見て、次回までに克服すべき課題をリストアップします。具体的には、先ほど述べたように間違えた問題の分析ですysmedia.jp。「どの科目の何分野で失点したか」「ケアレスミスはどこか」「時間配分は適切だったか」などを親子でチェックしましょう。例えば算数で計算ミスが目立つなら計算練習を強化する、社会で用語の覚え漏れがあれば短期集中特訓する、といった具合に、弱点箇所を具体化しますysmedia.jp。お子さん自身にも「なぜ間違えたのか」を考えさせ、解説を読んで理解させることが重要ですjisyusidou.com。この作業で「次に何をすべきか」が明確になります。
ステップ2:現実的な目標値を設定する – 課題が明らかになったら、次の模試や志望校合格に向けて具体的な目標値を決めます。ただ闇雲に「頑張るぞ!」ではなく、「算数の○○分野であと5点上乗せする」「次回偏差値を全体で3ポイントアップさせる」など、小さく具体的な目標を立てますysmedia.jpjisyusidou.com。例えば直近の模試で総合偏差値50だった子が志望校合格偏差値55を目指すなら、次の模試では52、その次は54…というように段階的に目標を設定します。各科目についても、「国語の長文問題で前回より設問ミスを2問減らす」「理科の計算問題で満点を取る」など、達成度を測りやすい指標を決めると良いでしょうjisyusidou.com。ポイントは、無理のない範囲で具体目標を区切ることです。「あと5点」という目標なら、お子さんも「それくらいならできるかも」と前向きに感じやすくなりますysmedia.jp。
ステップ3:学習計画に落とし込む – 設定した目標を達成するために、日々の勉強計画を調整・実行します。たとえば「社会の歴史分野であと10点取る」が目標なら、1週間で歴史年代の暗記を仕上げるスケジュールを組む、といった具合です。模試結果を参考にして優先順位をつけて学習時間を配分することが大切ですjisyusidou.com。全部を一度に完璧にしようとせず、弱点だった科目・単元からテコ入れしていきましょうjisyusidou.com。模試直後に判明した弱点は、新鮮なうちに復習することで効率よく克服できますjisyusidou.com。また、次回の模試日程から逆算して、「それまでに何をどれだけ終わらせるか」を親子でカレンダーに書き出すのも効果的です。
ステップ4:モチベーション管理 – 目標に向けて勉強を進める中で、お子さんのモチベーションを維持する工夫も必要です。模試の結果を活用して「前回よりここが伸びたね」「苦手が減ってきたね」と努力の成果を認め、励まし続けましょう。判定がBやCでも受かった先輩がいくらでもいること、本番まで伸びしろがあることを伝え、最後までチャレンジを続ける意欲を持たせてくださいysmedia.jp。親御さんも不安になる時期ですが、模試結果を冷静に分析して具体策に落とし込めば不安は行動に変わります。「悩んでいる暇はありません。一緒に計画を立てて実行あるのみ!」という姿勢で、前向きにサポートしていきましょうysmedia.jpysmedia.jp。
ステップ5:過去問演習との両立 – 志望校が固まっている場合、模試対策と並行して志望校の過去問演習にも取り組みます。模試の目標偏差値に届かなくても、志望校の過去問で合格点を取れる力をつけていれば合格可能性は充分にあります。筆者の考えとして、志望校がある程度固まっていれば過去問を解きまくることで「持ち偏差値以上」を目指すことも可能だと感じます。模試の偏差値はあくまで全体での立ち位置ですが、志望校対策を深掘りすることで偏差値に現れない力を発揮できることもあるのです。したがって、偏差値基準で学校を選ぶ場合でも、模試結果の目標設定には志望校対策の進捗も織り込みましょう。四谷大塚の合不合判定テストなどで提示される**合格可能性%**も参考にしつつ、最終的には過去問演習の手応えなども含めて目標を微調整すると効果的です。
以上のように、模試結果は次の目標と対策を定めるための格好の材料です。ただ結果に一喜一憂するのではなく、「原因と対策」をセットで考え、具体的な行動計画に落とし込むことが合格への近道となりますysmedia.jpysmedia.jp。模試を受けっぱなしにせず、結果を次に繋げる習慣を身につけましょう。それが偏差値や判定に振り回されず志望校合格を勝ち取る秘訣です。