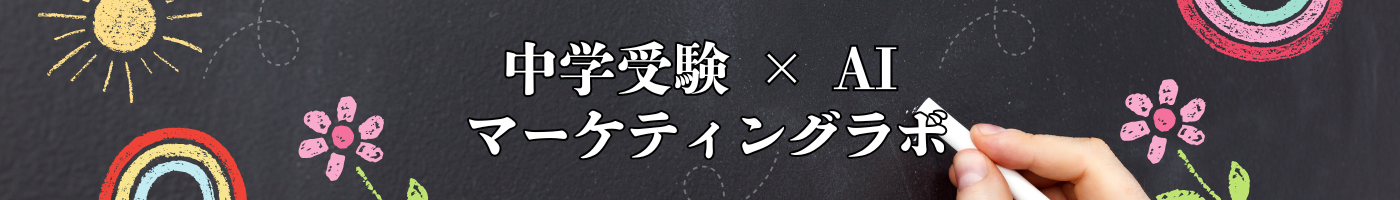中学受験を控えると、「習い事をやめて勉強に専念させるべきか?」と悩む保護者の方も多いのではないでしょうか。 しかし実は、これまで続けてきたスイミングやピアノ、英会話などの習い事は、中学受験の強い味方になり得ます。 (〖2024-2025年版〗子供に人気の習い事ランキング!男女別や習わせる理由も紹介 | 株式会社Fanssのプレスリリース)2024年の子どもに人気の習い事ランキングTOP3。1位はスイミング(水泳)、2位は英語・英会話、3位はピアノ (〖2024-2025年版〗子供に人気の習い事ランキング!男女別や習わせる理由も紹介 | 株式会社Fanssのプレスリリース) (〖2024-2025年版〗子供に人気の習い事ランキング!男女別や習わせる理由も紹介 | 株式会社Fanssのプレスリリース)。多くの小学生がこうした習い事に励んでおり、それぞれが受験勉強に活かせる要素を秘めているのです。最近ではAI(人工知能)を活用した学習ツールも登場し、習い事と組み合わせた新しい学習スタイルも注目されています。この記事では、親しみやすい語り口で 「習い事の意外な活用法」 を5つご紹介します。集中力や記述力、コミュニケーション力など、習い事で培った力を受験対策にどう転用できるのか、具体例や専門家のコメント、最新トレンドを交えて解説します。
1. 習い事で鍛えられた集中力を受験勉強に転用する方法

中学受験の勉強でまず武器になるのが集中力です。実は、習い事を通じて自然と集中力が鍛えられているケースは少なくありません。例えばそろばんでは、決められた時間内に大量の計算問題を解くため、子どもは一つひとつの問題に集中して取り組む習慣が身につきます (〖子どもの集中力を高める〗おすすめの習い事&集中力がアップする生活習慣 | こそだてまっぷ)。繰り返し計算する中で集中力や忍耐力が養われ、計算能力だけでなく記憶力・情報処理能力まで鍛えられるのです (〖子どもの集中力を高める〗おすすめの習い事&集中力がアップする生活習慣 | こそだてまっぷ)。また書道(習字)も、手本どおりに文字を書くために字形やバランスに気を配り、長時間黙々と筆を動かすので一つのことに集中する力が育まれます (〖子どもの集中力を高める〗おすすめの習い事&集中力がアップする生活習慣 | こそだてまっぷ)。こうして習い事で培った集中力や根気強さは、そのまま受験勉強の持久戦に活かすことができます。
では具体的に、どう勉強に転用するかを考えてみましょう。ポイントは、習い事での集中のリズムを勉強にも取り入れることです。例えばピアノを習っている子なら、30分間楽譜に向き合う集中のリズムが身についているはずです。その感覚で算数の問題演習も30分区切りで集中してみる、というように勉強の区切りを習い事の感覚に合わせると取り組みやすくなります。実際、ある保護者の方は「小学校入学後に始めたスイミングのおかげで、家で宿題に向かう際の気持ちの切り替えが上手になり、集中力がついたと実感している」と述べています (〖子どもの集中力を高める〗おすすめの習い事&集中力がアップする生活習慣 | こそだてまっぷ)。スイミングでは日常と違う動作に一つひとつ集中する必要があり、それが家庭学習にも良い影響を与えた例です。このように**「習い事モードの集中力」**を勉強時間にも応用することで、子どもはスムーズに勉強に没頭できるようになります。
さらに、「毎週決まった曜日・時間に習い事の練習を積み重ねて目標(発表会など)に挑む」という経験も貴重です。ピアノ教室では定期的に演奏会を開催することが多く、子どもは発表会という目標に向かって計画的に努力する力を身につけます (〖子どもの集中力を高める〗おすすめの習い事&集中力がアップする生活習慣 | こそだてまっぷ)。この計画力やコツコツ続ける力は受験勉強のスケジューリングにも役立ちます。習い事で「〇月の発表会までにこの曲を仕上げる」と計画的に練習した子は、「入試本番までにこの単元を完璧にする」と逆算して勉強を進めることにも抵抗がありません。習い事を通して得た集中力と計画力を上手に転用し、受験勉強を効率よく進めましょう。
2. スポーツや芸術系習い事が記述問題対策に効果的な理由
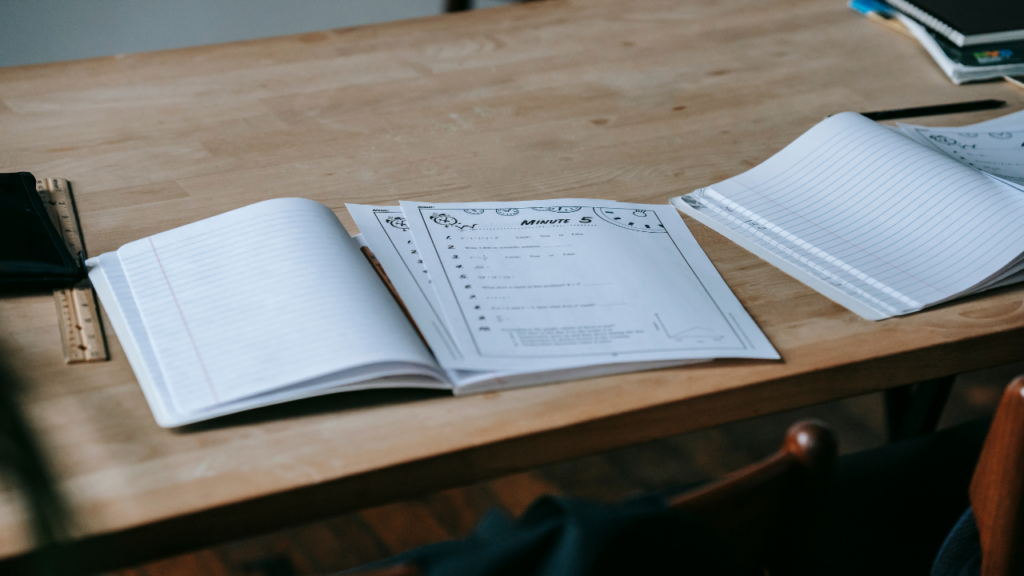
中学受験では、単に知識を答えるだけでなく記述式の問題(自分の言葉で解答を書く問題)が出題される学校もあります。国語の読解記述や、算数でも答えに至る考え方を説明させる問題など、論理的に考え、自分の言葉で表現する力が問われます。実はこの力こそ、スポーツや芸術系の習い事で養われる意外なスキルなのです。
まずスポーツの効果から見てみましょう。スポーツで体を動かすと脳が活性化され、集中力や記憶力が高まり勉強のパフォーマンス向上につながることが最新の脳科学研究で明らかになっています (学力と運動能力の相関関係 “運動ができる子は勉強もできる”はホント? | マナビコ-manabico | 親子に寄り添うエデュテインメントメディア)。運動神経と頭の良さは無関係どころか密接に関連しており、「運動ができる子は勉強もできる」という傾向もデータで示されています (学力と運動能力の相関関係 “運動ができる子は勉強もできる”はホント? | マナビコ-manabico | 親子に寄り添うエデュテインメントメディア)。つまり、運動系の習い事を続けてきた子は脳の働きが良くなり、記述問題に必要な思考の持久力や発想力が鍛えられている可能性があります。また、チームスポーツであれば試合中に瞬時に状況を判断し、自分で考えて動く力が身につきます。サッカーでは「なぜ今そのプレーを選択したのか?」を振り返り、次の戦略を論理的に考えることが求められます。実際、欧米のサッカーチームでは小学生であってもコーチから「なぜ今のプレーをしたのか説明してごらん」と問われることがあるそうです (スポーツにも勉強にも生きる「論理的思考力」を親子で鍛えよう – Z会おうち学習ナビ)。トップアスリートたちも論理的思考力を重視しており、5W1H(Why/When/Where/Who/What/How)を駆使して物事を考え、筋道立てて説明する訓練を積んでいるといいます (スポーツにも勉強にも生きる「論理的思考力」を親子で鍛えよう – Z会おうち学習ナビ) (スポーツにも勉強にも生きる「論理的思考力」を親子で鍛えよう – Z会おうち学習ナビ)。スポーツで培った「状況を分析し言語化する力」は、記述式の答案で自分の考えを論理的に述べる際に大いに役立つのです。
芸術系の習い事も記述力アップに貢献します。たとえば絵画や書道、音楽などの習い事では、感じたことを表現したり作品の意図を説明したりする場面があります。言語技術教育の専門家・三森ゆりか氏は、子どもにある絵を見せて「登場人物が悲しんでいるように見える」と答えたとき、「それはなぜそう思うの?」と問いかけ、根拠をすべて言語化させる指導を行っているそうです (スポーツにも勉強にも生きる「論理的思考力」を親子で鍛えよう – Z会おうち学習ナビ)。例えば「眉間にシワが寄っているから」「肩が落ちているから」といったように理由を引き出し言葉にしていく訓練を重ねると、「○○だから△△だ」という風に理由を添えて説明する癖が身についてきます (スポーツにも勉強にも生きる「論理的思考力」を親子で鍛えよう – Z会おうち学習ナビ) (スポーツにも勉強にも生きる「論理的思考力」を親子で鍛えよう – Z会おうち学習ナビ)。この能力こそ記述問題に必要なもので、問題文を読み「なぜそう言えるのか?」を考え、根拠を挙げて答案を書く力につながります。ピアノなど音楽の習い事でも、「この曲は明るい雰囲気だけどそれはどんな音使いから感じる?」と問われたり、自分なりの表現プランを考えたりすることで創造力と論理的思考力が養われます。さらに、スポーツ・芸術問わず何かに打ち込む経験は表現のネタにもなります。記述式の作文問題で自分の体験談を書く際も、習い事でのエピソードがある子は具体的で生き生きとした文章を書けるでしょう。「○○のおけいこで失敗したけれど工夫して乗り越えた経験」などは記述問題の格好の題材になります。
このように、スポーツや芸術系の習い事は記述力の土台となる思考力・表現力を育みます。「体を動かす時間があるなら机に向かっていた方が…」と思いがちですが、実は習い事で得たものが記述問題攻略の決め手になるかもしれません。受験直前でも上手に息抜きとして運動や芸術活動を取り入れ、脳を鍛えつつ表現力も磨くという一石二鳥の効果を狙いましょう。
3. 習い事で養ったコミュニケーション力を面接対策に活かす
中学受験では面接試験を課す学校も多く存在します。グループ面接や親子面接、個人面接など形式は様々ですが、いずれにしても子どものコミュニケーション能力や人柄が見られる場です。ここでも習い事の経験が強い武器になります。
特にチームスポーツや合同練習の習い事では、子どもは上下関係や集団行動の中でのコミュニケーションを自然と学んでいきます (アンケート「習い事の1番の効果は何だと思いますか?」その2|ミライコイングリッシュラボ)。野球やサッカー、バスケといったチーム競技では、コーチや仲間と意思疎通を図りながら協力することが欠かせません。そうした環境は子どものコミュ力を磨くのにうってつけで、「チームスポーツは指導者や仲間との対話が必要なためコミュニケーション能力を高める最適な場である」と指摘されています (スポーツはコミュニケーション能力や学力の向上に役立つ?おすすめのスポーツの習い事 | コエテコ byGMO)。習い事で先生の話をきちんと聞き、質問されたらはきはき答えるといった基本的態度が身についている子は、面接でも落ち着いて受け答えできるでしょう。また、英会話教室や書道教室など先生とマンツーマンまたは少人数で関わる習い事でも、目上の人と話す緊張感に慣れる効果があります。習い事の先生は学校の先生とはまた違う大人ですから、小さい頃からそうした「他人の大人」と接する経験を積むことで、面接官に対しても物怖じせず自分の言葉で話せるようになります。
面接ではしばしば「小学校時代に頑張ったことは何ですか?」と質問されます。このとき、打ち込んできた習い事がある子は強みです。5年続けたピアノや全国大会を目指した空手など、熱中した経験があれば面接官の前でキラキラと語ることができます。実際、難関校の一つである慶應義塾湘南藤沢中等部(SFC)の入試では、願書に「活動報告書」として小4以降続けている活動を一つ書かせ、それをベースに面接で深掘りする形式が取られています (小6まで続けた習い事が面接突破の鍵|娘慶應道 ~娘が中学合格するまでの歩み~/ケイ・チャン)。野球でもバレエでも琴でも何でも、「自信を持って話せること」を持っている受験生は非常に有利だと言われます (小6まで続けた習い事が面接突破の鍵|娘慶應道 ~娘が中学合格するまでの歩み~/ケイ・チャン)。逆に、小4以降塾一本で習い事を全てやめてしまった子は話せるネタが少なく、面接では苦労するケースもあるようです (小6まで続けた習い事が面接突破の鍵|娘慶應道 ~娘が中学合格するまでの歩み~/ケイ・チャン)。ある進学校では「勉強ばかりでなく『○○なら誰にも負けない』というものを持った子を採りたい」という方針があり、学科試験だけでなく面接での個性を重視しています (小6まで続けた習い事が面接突破の鍵|娘慶應道 ~娘が中学合格するまでの歩み~/ケイ・チャン)。習い事で培った技能や経験はまさにその子の個性であり、「この子は入学後も○○を頑張ってくれそうだ」と学校側にアピールする材料になるのです。
さらに、面接そのものに対する慣れという点でも習い事経験者は強いです。発表会や大会で人前に出た経験、習い事の先生とマンツーマンで話す経験などは、小学生にとって小さなプレゼンテーションや質疑応答の練習と言えます。実際の中学受験の面接でも、質問に対して自分の考えを伝え、時には聞き返されたことに答える「キャッチボール」が求められます (中学受験に活かせる小学生の習い事 | ロボ団ブログ)。ある学校の口頭試問(口述面接)では、40分の授業を受けた後に試問室で「何を学んだか」を質疑応答する形式が取られており、初めて接する内容でも柔軟に理解し、自分の言葉で伝える力が評価されています (中学受験に活かせる小学生の習い事 | ロボ団ブログ)。習い事で先生に質問したりアドバイスを求めたりした経験のある子は、このような場面でも自然とコミュニケーションが取れるでしょう。日頃からコミュニケーション力を養っておくことで、「面接も大丈夫、普段通りに話せばいいんだ」と子ども自身が自信を持てます。習い事で身につけた社交性や対話力は、受験の面接突破のカギとなるのです。
4. AI学習ツールと習い事を組み合わせた新しい学習スタイル

近年、教育業界ではAI(人工知能)技術を活用した学習ツールが登場しつつあります。中学受験生向けにも、AIが問題演習の弱点を分析して最適な問題を出してくれるアプリや、AIロボットが質問に答えてくれる教材などが出始めています。こうしたAI学習ツールと従来の習い事を組み合わせることで、忙しい受験期でも習い事を活かしつつ効率的に勉強する新しい学習スタイルが可能になっています。
一つ注目すべきは、AIによる個別最適化学習と人間の指導を融合させた塾のスタイルです。例えば大手学習塾の森塾が提供する「森塾DOJO」では、最新AI技術を搭載したタブレット学習と専任講師の個別指導を組み合わせる革新的なシステムを導入しています (AIと個別指導の融合 森塾DOJOが描く新時代の学習スタイル | 塾コレ)。まずAIが生徒一人ひとりの弱点を診断し、最適な学習プランを提案します。その上で講師が寄り添い、躓いているポイントを丁寧に解説したりモチベーションを引き出したりする仕組みです (AIと個別指導の融合 森塾DOJOが描く新時代の学習スタイル | 塾コレ)。AIの効率性と人間のきめ細やかさを両立させたこうした学習法により、短時間で効果的に学力を伸ばしつつ、子どものやる気も保つことができます。受験勉強の「質」を上げることで、習い事との両立もしやすくなるでしょう。
また、家庭学習の場面でもAIツールを習い事と組み合わせる工夫があります。例えばピアノ等のお稽古を続けながら受験勉強も頑張りたい子には、AI搭載のピアノ練習アプリを活用する方法があります。ドイツ発の「Skoove(スクーブ)」というアプリは、AIがユーザーの演奏をリアルタイムに聴いて分析し、正しく弾けた部分や改善点をその場でアドバイスしてくれます (しっかり学べるピアノ学習アプリ9選(2025年7月更新版) – Skoove)。これにより、わざわざ先生のところへ行かなくても好きな時間に質の高い練習が可能になります (しっかり学べるピアノ学習アプリ9選(2025年7月更新版) – Skoove)。習い事の時間を多少減らしても、AIが補って習熟度を維持・向上させてくれるわけです。同様に、英会話を習っている子ならAI英会話アプリで自宅にいながらネイティブ講師と話す練習ができますし、スポーツをやっている子ならフォームチェックにAI動画解析ツールを使うこともできます。習い事とAIツールを上手に組み合わせれば、習い事の効果をキープしつつ勉強時間を生み出すことができるのです。
スケジュール管理や学習管理にもAIやデジタルツールは役立ちます。共働き家庭向けの提案として、「家族で共有するデジタルカレンダーで習い事と塾・学校行事の予定を一元管理しよう」「子どもと一緒に学習記録アプリで毎日の勉強進捗を“見える化”しよう」といった方法が紹介されています (共働き家庭必見!子どものAI教育と他の習い事を両立させる7つのコツ|子供のためのAIスクール「ワクテック」)。実際に学習内容をグラフなどで視覚化して振り返ると、子どものメタ認知能力(自分の学習状況を客観視する力)が向上し、学習効率が約35%改善したという研究結果もあります (共働き家庭必見!子どものAI教育と他の習い事を両立させる7つのコツ|子供のためのAIスクール「ワクテック」)。習い事と勉強の両立には時間管理がカギですが、AI時代のデジタルツールを味方につければスケジュール調整も効率化できます。例えば、プログラミング教室に通って身につけたデジタルスキルで、自分の学習計画を子ども自身が管理する、といったことも可能です (共働き家庭必見!子どものAI教育と他の習い事を両立させる7つのコツ|子供のためのAIスクール「ワクテック」)。小学生の段階から複数の予定を自分で管理する経験は、将来の自己管理能力向上にもつながります (共働き家庭必見!子どものAI教育と他の習い事を両立させる7つのコツ|子供のためのAIスクール「ワクテック」)。
さらに、AI教育(プログラミング学習など)で培った力が他の習い事に波及効果を及ぼすケースも注目されています。 (共働き家庭必見!子どものAI教育と他の習い事を両立させる7つのコツ|子供のためのAIスクール「ワクテック」)によれば、まずAI教育と他の習い事は別々ではなく**「互いに補完し合う関係」と捉えることが大切だそうです。実際、プログラミングで身につく論理的思考力は数学の成績向上に直結するだけでなく、ピアノの譜読みや英語の文法理解にも良い影響を与えることが報告されています (共働き家庭必見!子どものAI教育と他の習い事を両立させる7つのコツ|子供のためのAIスクール「ワクテック」) (共働き家庭必見!子どものAI教育と他の習い事を両立させる7つのコツ|子供のためのAIスクール「ワクテック」)。プログラミング的な「順序立てて考える力」は楽曲を構造的に理解したり英文法のルールを整理したりするのに役立ち、ある調査では小学生の87%が「他教科の学習にも良い影響があった」と回答しています (共働き家庭必見!子どものAI教育と他の習い事を両立させる7つのコツ|子供のためのAIスクール「ワクテック」)。このようにAI学習と習い事をうまく組み合わせれば、各分野の学びが相乗効果を生み出し、受験勉強そのものも効率アップが期待できます。まさに「習い事×AI」のハイブリッド学習スタイル**で、限られた時間を最大限に活用しましょう。
5. 「習い事×AI」の実践事例とその効果
最後に、実際に**「習い事×AI」**を取り入れて成果を上げている事例をいくつかご紹介します。これは中学受験に限らず最近の教育トレンドでもありますが、習い事の現場にAI技術を導入することで子どもたちの学び方が大きく変わりつつあります。
一つ目の事例は、少年サッカークラブでのAI活用です。東京都多摩市の少年サッカークラブ「ムスタングFC」では、AI搭載カメラのVeo(ヴェオ)を導入しました (スポーツ×AI革命:子どもたちの未来を変える新しい練習方法|arata_suehira)。このカメラは試合中に撮影者がいなくてもボールの動きを自動追跡し、試合全体を録画してくれます (スポーツ×AI革命:子どもたちの未来を変える新しい練習方法|arata_suehira)。導入の効果はてきめんで、子どもたちは自分のプレーを客観的に簡単に見直せるようになりました (スポーツ×AI革命:子どもたちの未来を変える新しい練習方法|arata_suehira)。小学6年生の選手は「映像を見ればどう動くべきだったか、監督の指示の意味も一目で分かる」と語っています (スポーツ×AI革命:子どもたちの未来を変える新しい練習方法|arata_suehira)。AIのおかげで今まではコーチや親がビデオ撮影・編集に追われていた手間が省け、子ども自身が自分のプレーを振り返る時間に充てられるようになったのです。「なるほど、ここではこう動けば良かったのか」と視覚的に理解できることは、戦術理解や判断力の向上につながり、学習効率を飛躍的に高める可能性があります。このようにスポーツの習い事にAIを取り入れることで、子どもたちの自主的な振り返り学習が促進され、大きな効果を上げています。
二つ目の事例は、野球の練習メニュー作成にChatGPTを活用したケースです。私立品川翔英高校の硬式野球部では、練習できる時間や場所の制約をAIに入力し、効率的なメニューを提案してもらっているそうです (スポーツ×AI革命:子どもたちの未来を変える新しい練習方法|arata_suehira)。特に興味深いのは、AIが提案した「穴あきボールを使ったバッティング練習」です (スポーツ×AI革命:子どもたちの未来を変える新しい練習方法|arata_suehira)。穴の開いたカラーボールは芯で捉えないと遠くへ飛ばないため、正確なスイングを養うのに効果的な道具ですが、人間の指導者にはなかなか思いつかないような意外なアイデアですよね (スポーツ×AI革命:子どもたちの未来を変える新しい練習方法|arata_suehira)。このように、ChatGPTのような生成AIが創造的な練習方法を提案してくれることで、練習のマンネリ化を防ぎ新たな技術向上の糸口が得られています。実際にこの練習を取り入れたことでチームの打撃力アップにつながったとしたら、まさにAIがもたらした成果と言えるでしょう。受験勉強でも、例えば苦手分野克服のためのユニークな勉強法をChatGPTに相談してみる、といった応用が考えられます。人間の発想にAIのアイデアをプラスすることで、より効果的で斬新な学習メニューを実践できるのです。
三つ目の事例は、教育機会の格差是正にAIを活用しているケースです。プロバスケットボールリーグ(Bリーグ)は、離島の中学校バスケ部向けにソフトバンクの「AIスマートコーチ」というスポーツ支援サービスを提供しました (スポーツ×AI革命:子どもたちの未来を変える新しい練習方法|arata_suehira)。離島など指導者が不足しがちな地域でも、AIが内蔵された動画お手本やフォーム解析によって、都会のクラブと同等の指導が受けられるようにサポートしたのです。これにより、地理的なハンデを抱える子どもたちでも質の高い練習が可能となり、地域間の学習環境の差を埋める効果が期待されています (スポーツ×AI革命:子どもたちの未来を変える新しい練習方法|arata_suehira)。同様に、塾や家庭教師が周りに少ない地域の受験生でも、AI搭載のオンライン学習サービスを使えば都市部と遜色ない指導が受けられる時代になりつつあります。習い事×AIの実践は、このように子どもたち全体の学びの底上げにも寄与しているのです。
以上のような事例から、「習い事×AI」は単なる未来の夢物語ではなく、すでに現実のものとなっていることがお分かりいただけるでしょう。AIの導入によって、これまで人手や時間の制約で十分にできなかった振り返り学習や効率的な練習が実現しつつあります。中学受験の世界でも、AIによる過去問分析や解説、自動添削などが登場しており、これらを習い事と組み合わせて活用すれば飛躍的な効果が見込めます。大切なのは、人間の講師やコーチとAIの得意分野をうまく組み合わせ、子どもにとって最適な学習環境を整えることです。習い事とAI、双方の力を借りて受験対策をアップデートしていきましょう。
まとめ: 習い事を賢く活用して中学受験を乗り切ろう
中学受験期の習い事の扱い方について、5つの視点から見てきました。集中力・記述力・コミュニケーション力といった受験に不可欠な力は、これまでお子さんが取り組んできた習い事の中にも確実に息づいています。習い事をただの「お稽古ごと」で終わらせず、「これは受験にも役立つんだよ」と視点を変えてみると、親も子も習い事へのモチベーションが一段と上がるでしょう。また、AI学習ツールとの組み合わせという最新トレンドも押さえることで、忙しい受験期の時間を有効活用できる可能性が広がります。習い事と勉強、一見両立が難しそうに思えますが、上手にハイブリッドすることで相乗効果が生まれることがお分かりいただけたかと思います。
最後に重要なのは、お子さん本人が興味を持ち楽しんで取り組めることを続けるという点です。 (AI時代に取り残されない!小学生の習い事ランキングTOP7と選び方|子供のためのAIスクール「ワクテック」)でも強調されているように、AI時代に求められる創造力・思考力・コミュニケーション能力などは、結局のところ子どもが主体的に「楽しい!もっとやりたい!」と思える環境でこそ伸びていくものです。無理に習い事を増やしたりAIツールを導入したりする必要はありません。これまで培ってきた習い事を大切にしつつ、その延長線上で受験勉強に活かせる工夫をすることがポイントです。習い事で得た力を信じてあげれば、お子さんも「○○で頑張った自分なら受験も頑張れる」と自信につながります。ぜひ親子二人三脚で習い事を賢く活用し、笑顔で中学受験を乗り切ってくださいね。きっと習い事での経験が、お子さんを合格へと後押ししてくれることでしょう! (AI時代に取り残されない!小学生の習い事ランキングTOP7と選び方|子供のためのAIスクール「ワクテック」)