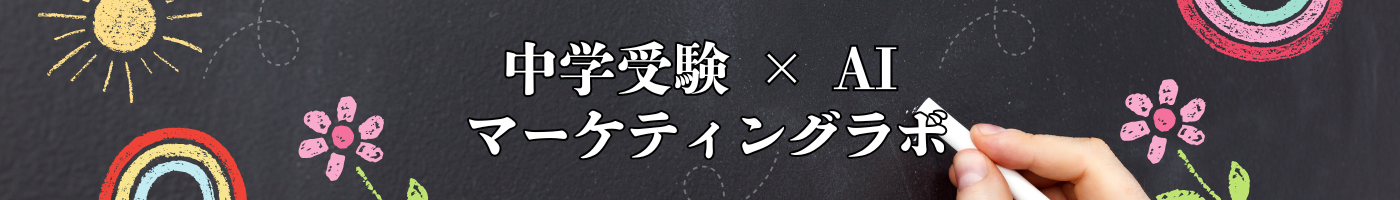習い事を続けるか、やめるか?判断のポイントを徹底解説
小学生の約8割が何らかの習い事に通い、平均で週にほぼ2つを掛け持ちしているといわれます。月謝は1万6,000円台が平均で、1週間あたり10時間以上取り組む子も1割弱に上るとされ、費用面だけでなく時間面での負担も大きいのが現状です。さらに学年が進むにつれて、塾や模試など受験関連のスケジュールが増えていくため、「いつ、どうやってやめるか」を考えるのは中学受験家庭にとって切実なテーマといえます。
習い事を継続する場合は、子どもの意欲が維持できるかをチェックするとともに、家庭のリソース(送迎や費用など)を冷静に見直す必要があります。逆にやめる場合には、子どものモチベーションや交友関係、さらにはこれまで積み上げてきたスキルがどう変化するかを見極めることが大切です。単に「受験だから」と一律にやめさせてしまうと、子どもにとって大事な自己肯定感や習慣が損なわれる可能性があります。「中学受験で優先すべきは何か」「継続した場合のメリット・デメリットはどうか」といった観点で、家族で丁寧に話し合うことをおすすめします。
また、最近ではオンライン型の習い事や、自宅でもスキルを伸ばせる教材が増えています。ピアノや英語などはオンラインレッスンの普及が進み、時間や場所の制約が減ってきています。こうした選択肢をうまく活用すれば、受験と両立しつつも無理なく続けられるかもしれません。ただし一方で、家の中で全てを完結させようとすると、親子ともにオンオフの切り替えが難しくなるリスクもあります。実際にオンライン習い事を導入してみたものの、「子どもが集中できない」「画面越しの指導に物足りなさを感じる」という声もあり、一長一短だと言えます。家庭環境との相性も大事ですから、事前に体験レッスンなどを利用して子どもが続けやすいかどうかを確かめておくと良いでしょう。
習い事をやめるタイミングで起こりやすいトラブル対処法
1. 教室側との行き違い

習い事をやめる際に、よく問題になるのが「年度途中の退会は月謝返金なし」「退会の申し出は2か月前まで」などの規定です。規約や契約書をしっかり確認せずにバタバタとやめてしまうと、退会時期によっては損失を被ったり、教室との関係がこじれたりしかねません。特に音楽やスポーツ系のスクールでは年間計画を立てていることが多く、途中退会は教室側にも影響が及ぶため、家族だけで判断するのではなく、早めに担当者と話して意向を伝えることが円満退会のポイントです。
また、もし教室やスクールとの行き違いが生じた場合でも、感情的にならず、書面やメールでやり取りを行っておくと安心です。口頭のみで話を進めると「言った・言わない」のトラブルに発展しやすいですし、教室との今後の付き合いにも影響が出ます。書面やメールでやり取りを残しておけば、お互い納得のうえでスムーズに退会できる可能性が高まります。
2. 子どもの“辞めグセ”懸念
保護者が最も心配するのが、「途中で投げ出す癖がついてしまうのでは?」という点です。子どもが「もうやめたい」と言い出した理由が、ただの一時的な感情なのか、根本的に合わないのかを見極めることが必要です。専門家の多くは「一度納得してやめた経験が、むしろ次の挑戦へのモチベーションになる」と指摘していますが、一方でコロコロ変える習慣が子どもの性格に悪影響を与えないかを、きちんと話し合う姿勢も大事です。
もし習い事をやめる場合は、「代替の挑戦機会」を確保するのがおすすめです。例えば運動系の習い事をやめるなら、週末に家族でスポーツを楽しむ時間を作る。音楽レッスンを中断するなら、家で楽しめる演奏アプリを導入してみるなど、完全に“ゼロ”にせず、ある程度の継続要素を設定しておくと、子どもが自らの興味をうまくスライドさせやすくなります。
3. 友人関係のしこり
同じ習い事をしている仲間との関係も見逃せません。特にチームスポーツや合奏など、集団の中で協力が求められる場では、誰か一人が抜けるとチームのバランスが崩れ、残る子たちの負担が増える可能性があります。子どもが気まずい思いを抱えないよう、保護者同士が事前に情報を共有し、退会する理由やタイミングについてオープンに伝えるのが望ましいです。
また、子ども同士でも「何でやめるの?」「裏切りじゃないの?」といった言葉が飛び交ってしまうことがあります。その際は、親がうまくフォローに入るとともに、子どもの気持ちを丁寧に聞き取ってあげると安心感につながります。受験が迫っているならその事情を素直に話し、別の機会で一緒に遊ぶなど、関係を続ける工夫があれば相手の理解を得やすくなるでしょう。
「辞める」と決めた習い事から得られた意外な収穫とは?
- 集中力の再配分
習い事をやめると、そのぶん学習に充てられる時間が増えるため、成績向上に直結するという声は少なくありません。ただし意外な点として、習い事で培った「タイムマネジメント力」や「短時間で成果を出す集中力」が生きるケースも多いといわれます。長時間勉強に取り組むだけでなく、「いかに効率よく取り組むか」を子ども自身が意識できるようになると、受験対策の質が高まりやすいのです。 - 自己決定感の向上
「自分で辞めると決めた」という経験は、自分で物事を選び取るプロセスが学べる貴重な機会でもあります。大人が一方的に「受験に専念するからやめるよ」と決めるのではなく、「続ける・やめるのメリット・デメリット」を共有しながら話し合い、子どもが最終的な判断を下すことが理想です。これによって、自己決定感と責任感が高まり、何事にも主体的に取り組む姿勢が育まれます。 - 経済的・心理的ゆとり
習い事には、月謝や交通費、場合によっては道具代など、さまざまな出費が伴います。特にスポーツ系の習い事では大会や遠征費用がかさむ場合もあり、家計を圧迫する一因となりがちです。やめることで発生する経済的なゆとりは、学習塾や教材への投資に回したり、家族の息抜きのためのレジャーに使ったり、よりメリハリのある使い方に転換できるメリットがあります。また、送り迎えや準備に費やしていた親の時間的負担が減ることは、精神的にも余裕をもたらす要素です。結果として、親子の会話やコミュニケーションに割く時間が増え、親子関係が向上する可能性もあります。
習い事終了後の時間を有効活用するAIサポートツール
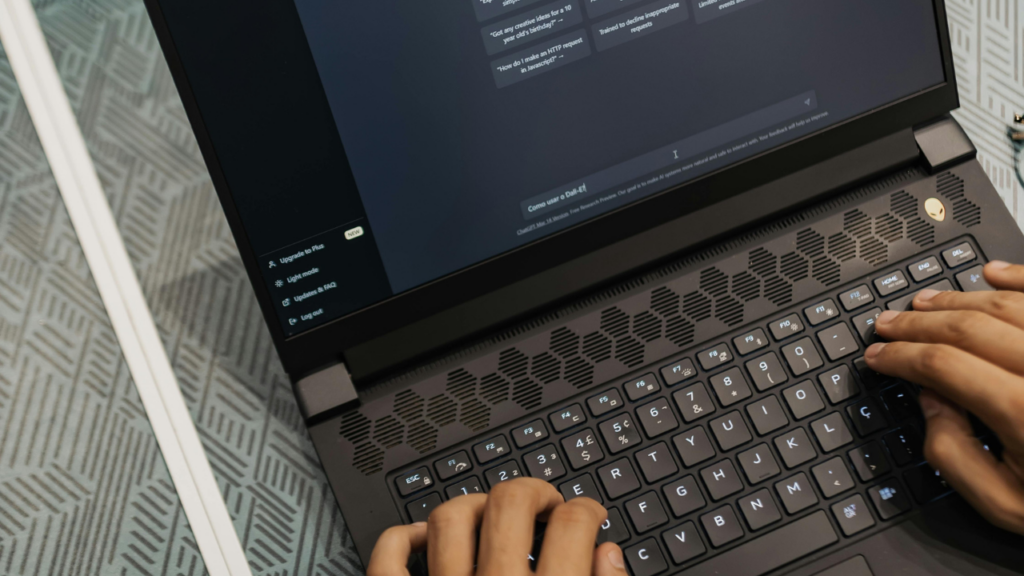
受験準備は学習量だけでなく、学習の質をどう高めるかが鍵になります。最近はAIが子どもの苦手分野を分析したり、最適なカリキュラムを提案したりするサービスが急速に増えています。習い事をやめて空いた時間を、こうしたデジタル学習ツールで効率よく使うという家庭も増えています。
マジタク
AIが子どもの苦手分野を分析し、プリンターと連携して毎朝オーダーメイドの問題を自動印刷する仕組みが特徴です。利用者の9割が「苦手克服を実感」、6割が「学習継続が楽になった」と回答しており、親がわざわざ問題を用意する手間も減らせます。視覚的に成果を確認できるため、子どものモチベーション維持にも一役買ってくれます。
atama+(Z会 AI基礎完成コース)
こちらはタブレット一台で完結する学習サービスです。解答履歴をAIが解析し、最短ルートで弱点を補強してくれる自動カリキュラムが大きな魅力。通塾時間を確保しづらい家庭にとっては、「塾に行かなくても苦手をフォローできる」という心強さがあります。受験まで時間が限られた小学高学年の子に向いていると好評です。
Studyplus連携アプリ
学習した時間や教材を自動で集計し、週単位でグラフ化してくれる学習管理ツールです。保護者が子どもの進捗や弱点をリアルタイムで把握しやすく、具体的な声かけのタイミングも計りやすいとされています。学習ログが可視化されることで、子ども自身も「やった量」を認識しやすくなり、達成感が高まりやすいのが特徴です。
家庭での意思決定プロセスと子どものモチベーション維持法
- 親子ミーティングを定例化
週1回15分でも“家庭会議”を設け、受験の目的や習い事の意義、今後の目標などを共有する場を作るのがおすすめです。ここで大切なのは、子どもが「自分の意見を言える」雰囲気を作ること。親が大人目線で結論を押し付けるのではなく、疑問点や不安をじっくり聞いてあげることで、子どもは自分の意思を尊重されていると感じ、学習や決断に対して前向きな気持ちを育むことができます。 - ロードマップの可視化
6年夏までに偏差値○○を達成する、秋以降は過去問対策に集中する、といった具体的なマイルストーンをホワイトボードやカレンダーに書き出すと、子どもが「今は何をすべきか」を理解しやすくなります。習い事を辞めるタイミングが決まっているなら、その後に増える学習時間でどんな勉強に取り組むかも具体的に示しておくと、辞めた後の空白時間が“成長の余白”として積極的に活用されるようになります。 - 小さな成功体験の連鎖
子どもは大きな目標だけを掲げると途中で息切れしやすい傾向があります。そのため、模試で偏差値を5上げる、過去問の正答率を10%上げるなど、短期で達成可能なゴールを複数設定しましょう。達成ごとに具体的なご褒美を用意するのも効果的です。心理学的にも「行動→達成→報酬」のサイクルを短く回すことで継続率が上がるとされており、小学生の子どもには特に有効です。 - 「やらされ感」を減らす工夫
親に言われたから勉強する、という状態が長く続くと、子どもはモチベーションを失いやすいです。そこで、学習計画作りに子ども自身が参加する、教材を子どもが選ぶなど、意思決定プロセスに少しでも子どもを巻き込む工夫が必要です。小学校高学年になれば、ある程度の情報を与えれば自分なりの計画を立てられる子も多いですし、なにより自分で考えたスケジュールには責任感が生まれます。「自分で作ったからこそ守りたい」と思えば、親の声かけが減っても学習を続けられるでしょう。
まとめ

受験と習い事の両立か、いっそやめるか——最終的な判断基準は「本人がどうしたいか」に尽きるという点は変わりありません。親はあくまで情報提供者・環境整備者の立場を取り、子どもを子ども扱いしないスタンスを維持することが大切です。もし親が「受験だから絶対やめなさい」と一方的に結論を押し付けると、子どもが「自分の人生なのに勝手に決められた」という不満を抱き、うまくいかなかったときに親を責める可能性も否定できません。一方で、「やめたほうがいい理由」「続けるメリットやデメリット」を整理して提示し、最終決定は子どもに委ねれば、結果がどうであれ自分で選んだ道として納得感を持ちやすくなります。
また、ここで育まれる「自分で考え、自分で決める力」は、中学受験だけでなく、その先の高校・大学受験や社会人になってからのキャリア選択など、さまざまな局面で役立つ重要なスキルです。大人になる前の貴重な体験のひとつと捉えて、むしろこの時期に“意思決定”を習慣づけるほうが将来的にはプラスに働くとも考えられます。勉強はもちろん重要ですが、それ以上に「自分の考えを持ち、行動し、結果に責任を持つ」という姿勢が身につけば、子どもは受験以外の大きな収穫を得られるでしょう。
結局のところ、受験そのものは通過点であり、子どもの成長は受験の先もずっと続きます。習い事を続けるかやめるかという選択が、その成長をどう支え、どんな経験値を蓄えるのかを想像しながら、家族みんなで話し合って結論を出せるのが理想的な形ではないでしょうか。
参考サイト(10件)
- ベネッセ教育情報「2024年版 小学生に人気の習い事ランキング!」
- マイナビ子育て「習い事をしている小学生は約8割」
- ダイヤモンド教育ラボ「中学受験で習い事はいつまで続けるべき?」
- まなチャンネル「中学受験と習い事は両立できる?」
- 東洋経済オンライン「『習い事をやめたい』という子への対応」
- iTeen経堂「小学生が習い事を辞めたい時の対処法」
- PR TIMES「AI学習支援アプリ『マジタク』」
- Z会「AI基礎完成コース(atama+)」
- ベネッセ教育情報「子どもが自分で意思決定する力を育むには」
- スポーツ庁「幼児期の運動習慣が与える影響」